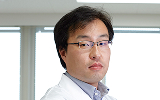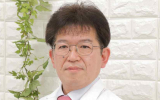令和6年度CAMaD 若手研究者海外派遣支援事業 活動報告
- Other
CAMaDでは、次世代のワクチン開発や感染症学・免疫学研究をリードする若手研究者の育成を重要なミッションの一つに掲げており、これらの分野において研究を行う若手研究者を対象に、海外での研究活動に参画するための支援を行っています。今回は令和6年度の採択者を順番に紹介いたします。
学 会 名:43rd Annual Meeting of American Society for Virology
開 催 地:Greater Columbus Convention Center(アメリカ合衆国 オハイオ州コロンバス)
渡航期間:2024年6月23日~2024年6月30日(8日間)
大阪大学微生物病研究所 ウイルス免疫分野 助教
小瀧 将裕